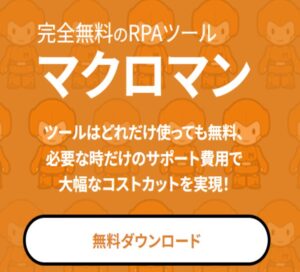今まで大変つらい思いして、大変苦労してきたのだから、私は障害年金を受給できない?もし受給できたとしたら障害年金をいくら受給できるの?
障害年金がいくら受給できるか?について解説します。(令和7年4月から版)
貴方は障害年金をいくら受給できる?
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。また、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できる方もいれば、障害基礎年金だけしか受給できない方もいます。
5万円~20万円以上になる場合がございます。

貴方の受給できる障害基礎年金の受給額は?
国民年金の障害年金制度である障害基礎年金は、「障害基礎年金+子の加算額」で支給されます。そして、障害基礎年金は、障害等級が1級と障害等級2級しかありませんのでご注意下さい。
障害基礎年金の年金額について
障害基礎年金の年金額は、生年月日と障害等級で異なります。
(1)障害等級1級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,039,625円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円 + 子の加算額 |
(2)障害等級2級
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 + 子の加算額 |
子の加算額について
(3)子の加算額
更に、「子の加算額」の対象となる子は、障害年金を受給される方に①生計を維持されていることが必要です。※生計維持関係があれば同居までは求められていません。
そして。更に、②18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子が、子の加算額の対象となります。
このようなお子さんがいらっしゃる場合は、必ず障害年金を請求する際に合わせて申請をしましょう。
| 2人まで | 1人につき239,300円 |
| 3人目以降 | 1人につき79,800円 |
障害基礎年金の受給例:年金額一覧表
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方の場合
| 障害等級 | 家族構成 | 支給額 |
| 1級 | 子なし | 1,039,625円 (月額 86,635円) |
| 1級 | 子1人 | 1,278,925円 (月額 106,577円) |
| 1級 | 子2人 | 1,518,225円 (月額 126,518円) |
| 1級 | 子3人 | 1,598,025円 (月額 133,168円) |
| 2級 | 子なし | 831,700円 (月額 69,308円) |
| 2級 | 子1人 | 1,071,000円 (月額 89,250円) |
| 2級 | 子2人 | 1,310,300円 (月額 109,191円) |
| 2級 | 子3人 | 1,390,100円 (月額 115,841円) |
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方の場合
| 障害等級 | 家族構成 | 支給額 |
| 1級 | 子なし | 1,036,625円 (月額 86,385円) |
| 1級 | 子1人 | 1,275,925円 (月額 106,327円) |
| 1級 | 子2人 | 1,515,225円 (月額 126,268円) |
| 1級 | 子3人 | 1,595,025円 (月額 132,918円) |
| 2級 | 子なし | 829,300円 (月額 69,108円) |
| 2級 | 子1人 | 1,068,600円 (月額 89,050円) |
| 2級 | 子2人 | 1,307,900円 (月額 108,991円) |
| 2級 | 子3人 | 1,387,700円 (月額 115,641円) |

貴方の受給できる障害厚生年金の受給額は?
障害厚生年金の年金額は、一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。
| 障害等級 | 金額 |
| 1級 | 障害基礎年金
+ 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(239,300円) |
| 2級 | 障害基礎年金
+ 報酬比例の年金+配偶者加給年金(239,300円) |
| 3級 | 報酬比例の年金
昭和31年4月2日以後生まれの方:最低保障額 年額623,800 円 昭和31年4月1日以前生まれの方:最低保障額 年額622,000 円 |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分 ※一時金 |
①障害厚生年金の年金額は、上記の通り、主に報酬比例の年金額である為、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。ですので、障害基礎年金の年金額のように決まっていません。
②報酬比例部分を算出する際、厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たない場合においては、300月として見なされて計算が行われます。
③障害認定日が属する月の翌月以降の被保険者としての期間については、年金額を算定する際の基礎には含まれません。
(1)報酬比例部分について
報酬比例部分というのは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のすべての給付において、年金額を算出する際の基本となる要素です。これは、年金制度への加入期間や過去の給与などに基づいて算定されるもので、その計算方法は以下の通りとなっております。
報酬比例部分 = A + B
共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
平均標準報酬月額は、平成15年3月より前の加入期間に関して、計算の根拠となる各月の標準報酬月額の合計額を、平成15年3月以前の加入期間の月数で除することによって算出される金額です。
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降に加入していた期間について、計算の基礎として使用される各月の標準報酬月額および標準賞与額を合算した総額を、平成15年4月以降の加入期間で除して求められる金額のことです。
(2)従前額保障について
従前額というのは、平成6年の基準に基づいて標準報酬を再評価し、それによって算定された年金額のことを指します。上記の計算式で求めた金額が従前額(以下の計算式によって算出される金額)より少ない場合には、この従前額が報酬比例部分の金額として採用されることになります。
報酬比例部分(従前額)=( A + B )× 1.061
・昭和13年4月1日以前に生まれた方は、「1.061」ではなく、「1.063」で計算します。
・共済組合の加入歴がある方における報酬比例部分の年金額に関しては、各共済加入期間における平均報酬月額あるいは平均報酬額と、その加入期間の月数に対応する金額、並びにその他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と、その加入期間の月数に対応する金額を、それぞれ別々に算出することになります。
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
・給付乗率(7.5/1000)は、昭和21年4月1日以前に生まれた方の場合だと異なりますのでご注意下さい。
・平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の期間において加入していた際の、計算根拠となる毎月の標準報酬月額を合計した金額を、平成15年3月より前の加入期間の長さで除したものを指します。
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
・給付乗率(5.769/1000)は、昭和21年4月1日以前に生まれた方の場合だと異なりますのでご注意下さい。
・平均標準報酬額というのは、平成15年4月以降に加入していた期間に関して、計算のベースとなる月々の標準報酬月額と標準賞与額を全て足し合わせた総額を、平成15年4月以降の加入していた期間数で割ることによって算出される金額です。
(3)配偶者加給年金額について
障害厚生年金の受給している人によって生計を維持されて65歳に達していない配偶者がいる場合に加算対象となります。
申請や手続きについてお悩み等ございましたら、経験豊富な社労士にお気軽にご相談下さい!
この投稿記事についての《問合せ》は
●「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社労士相談ナビ / 運営:社会保険労務士法人ファウンダー
所在地 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
連絡先 011ー751-9885