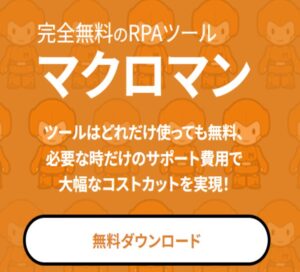皆さんは、将棋をやったことありますか?
しばらくやっていなかったのですが、子供が将棋に興味をもったことを切っ掛けに、最近は毎日やっています。
将棋をやりながら、ビジネスに置きかけて考えてみたり、自分の思考習慣、癖を確認しています。
そこで私なりに気付いたことを少しまとめてみましたので紹介したいと思います。

ビジネスにおける飛車・角とは?
「飛車」と「角」は、それぞれ縦横に、斜めに盤上を動けます。このような動きって、ビジネス上はどのような動きに該当するのだろうかと疑問が湧いた。時流、トレンド、影響力ある人などと譬えることが出来るかもしれない。皆さんはどう思いますか?
「飛車」「角」って「外交力」、それに比べて一歩づつしか動けない地道な「金」「銀」は「政治力」に譬えることができるかもしれない。
「飛車」「角」は離れている程効果を出せるように思う。私の場合、離していないと直ぐに取られてしまう場面が多い(笑)
見え見えの外交も効果を生む場合もあるのだろうけど、見えていないときの方がはるかに脅威だ。
「兵は詭道なり」
こんな言い方ができると思う。
将棋は、相手に利益で誘導して、自分にとって有利な状況を作って勝つゲーム。
そういう意味では、競合相手との駆け引きにおいて、相手に何を見せ、何を取らせて、自分は何を得るのか?
そして最後の局面で総決算して、どちらが勝つのかが決まる。
100戦中99敗でも、最後の1勝をどちらが勝ち取るのか?
「兵は詭道なり」(孫子の兵法)のそのまま。
「攻め」と「守り」のバランス
将棋で、相手陣地に攻めに攻めると、「先に行く駒」と「遅れる駒」が出て来る。
その「先に行く駒」と「遅れる駒」との間を抜けて来る相手の駒によって、負けにつながることがある。
この間隙こそビジネスでもありがちな「油断」。
そのことが結果して足元をすくわれる結果となる場合がある。
どんなに有利に戦局を進めていたとしても、一呼吸して守りを見直す必要がある。将棋では絶対に大将の守りと退路の確保は忘れてはならない。
これをビジネスに譬えると、リスクマネジメントであったり、社員教育だったり、その組織にとって不足しているものと言えるかもしれない。
才能ある人材を活かす組織
将棋で「歩」が「歩」のままなら戦略上使う場面が限定される。
但し「歩」は「歩」であることに意味もあって、「歩」として活躍できるから他の駒が活躍できる。
これと同じように、特別秀でた才能がない人材でも、活躍できる場を作ってあげることで、才能ある人材を始めて活かすことができる。
再現性が高いビジネスモデル
将棋で「歩」が「歩」のままなら戦略上使う場面が限定される。
でも「歩」が格上の活動ができる「と」になると、話は別で、活躍の幅大きく変わる。
このような再現性の高いモデルが、有るか無いかでは事業として大きな違いが生む。
その環境を作れる切っ掛けの1つが DX だと思う。
ビジネス上の「限界的存在」
ドラッカーが言っている「限界的存在」って、極端な話、将棋で例えると「王将」を盤の端に置くことだと思う。
要は、選択肢の少なさであり、市場における自社の立ち位置のことである。
自分の型を発見
将棋の出だしって「自分の型」を見つけた方が展開しやすいと思う。
ビジネス上でも同様。
だけど、一度勝利の思考パターンが出来ると、何度か失敗しないと、同じやり方では成功できないと自覚ができない。
一度自覚できたら、人によって強弱はあったとしても、トライ&エラーを繰返して成長していけるんじゃないかな。
環境変化に気付かない「茹でカエル」の中には、元成功者もいるのかもしれませんね。
まとめ
将棋に限らず、直接関係ないように見えてもつながっているものが多いのでないかなって思います。
皆さんのご意見も知りたいです。
宜しければ教えて下さい。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号