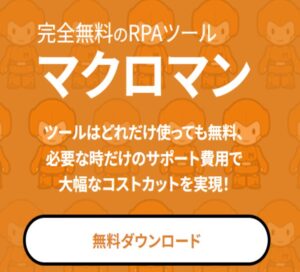本日、ピアノをやっている娘のピアノ教室へ同行して来ました。
曲がベートーヴェンの悲愴でした。
後ろに座りながら、ベートーヴェンの作曲したものは、低音のものが多いのかな?
どうやって作曲したのかな?など、疑問がわいて、終いにはベートーヴェンの耳の状態は障害等級何級相当だったのかな?
これは職業病の一種かもしれませんが、調べてみることにしましたのでご紹介します。
ベートーヴェンの耳についての記載をネット検索
調べると、20歳後半から難聴が悪化して、30歳の頃にはほとんど聞こえなくなり、40歳では全聾となったそうです。
・・・・・・ということは、40歳で障害年金1級ということですよね。
かくして私の疑問は直ぐに解決をしてしまったようです(笑)
ですが、『全聾』は文字からすると「全く聞えない」ってことですけど、念の為、これも調べてみました。
全聾とは
身体障害者福祉法の分類によると、『両耳の聴力レベルがそれそれ100以上のもの(両耳全聾):2級』とありました。
どうやら『両耳の聴力レベルがそれそれ100以上のもの』が、『全聾』と診断されるようです。
だとすると、やはり『障害年金の障害等級1級』相当だったようですね。
どうやって作曲をしたのか?
では、耳が聞こえなくなったベートーヴェンがどうやって作曲したのか?
ピアノに耳をあてて作曲をしてたとは聞いたことはありますが・・・・
ベートーヴェンの知人のベッティーナ・ブレンターノは、下記のように記しています。
「それに加え彼は難聴でしかも(近眼で)殆ど何も見えないのです。彼はまさに作曲していながら全く聴こえないのです。彼の目は全くあらぬ方をさ迷っているのです。全和音が彼の頭脳のなかで動いていて、その上に彼は感覚を適合させていき、曲ができていきます。ですから、彼は外界と結び付けているもの(顔と耳)と、全く切り離されており、従って深い孤独の中に生きています」(「ベートーヴェン書簡選集」より)
ベートーヴェン自身は、散歩中などに、曲の楽想(イデー)が音としてやって来ると語っています。
「一つの楽想が心に来るとき、私には常にそれが楽器の音で聴こえる」
「私はそれ(イデー)を追跡してつかまえる。すると、そいつが私から逃れて、沸騰している塊の中に消え去るのを見る。再び熱意を振るい興して、それをもう一度とらえる。私はもう、どうしてもそれを失くすることができないのです。恍惚の痙攣の中で、それを私はあらゆる変調に多様化しなければならない」(「ベートーヴェンの生涯」より)「頭の中では加工が始まって広まり、狭くなり、高くなり、そして深まる。(中略)それは上の方に昇り、育ち、私はそのイメージを完全に耳にし、目にし、丸ごと私の内面で受けとめ、あとは書きとどめるだけになります」(「ベートーヴェン」フリッツ・ツォーベライ著より)
上記の内容を読むと、単純にピアノに耳を当てながら作曲していたとは思えない内面的な瞑想的なプロセスがあったようです。
だからこそ、彼の作品なんですよね。凄すぎる。
ま と め
ベートーヴェンに関しては、耳が聞こえなくなったけど、それ以上に彼には生きる目的があったように思います。
だからこそ、耳が聞こえなくなっても全力で音楽に向き合えたのだと思います。
私も、そのようなに全力で向き合っていきたいと改めて決意をさせて頂きました。
ありがとうございます。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
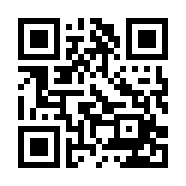
●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。
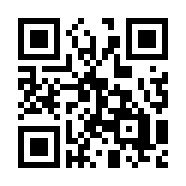
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。
聴力障害の方の生活で困ること
聴力障害のある100人に「どのようなことが困りますか?」と質問。
下記はその回答です。
1、公共交通機関(バスや鉄道等の車内)のアナウンス
2、エレベーターの非常通報ボタン
3、110番、119番の緊急ダイヤル
4、災害時の避難所や町内アナウンス
5、マスクで口元が見えない
6、クレジットカードが紛失した際の連絡
7、職場での会議など大人数の会話
8、「話せる=聞こえる」の勘違い
9、病院の待合室での呼び出し
10、ドライブスルーでの注文
何かの参考して頂けたらと思います。